派遣先の「面接」は禁止されています
派遣先企業は、紹介予定派遣を除いて、派遣労働者を特定する(選別する)行為をすることが禁止されています。
派遣先企業が派遣会社と派遣契約を結んだとき、誰を派遣させるかは派遣会社が労働者のスキル等を勘案して決定します。
派遣労働者の就業の機会を守るため、派遣先企業が派遣労働者を選ぶことはできないのです。
では具体的に、派遣労働者を特定する行為にはどのようなものが挙げられるのかを見ていきましょう。
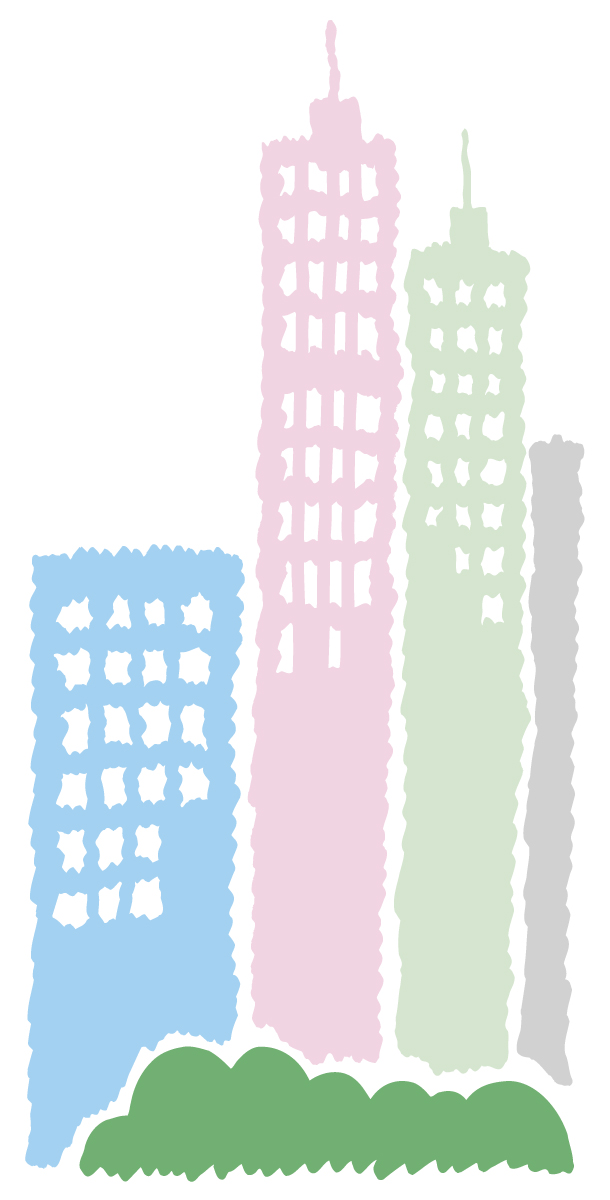
派遣労働者を特定する行為とは
事前面接を行う、履歴書を提出させる、年齢や性別を限定する、適性検査や筆記試験を行う、などがこれに当たります。
また、業務に関係しない質問をすることも、労働者を特定する行為に当たり、禁止されています。
例えば氏名や年齢、住所や家族構成といった個人情報のほか、結婚や出産について、宗教や信仰の有無について質問することも禁止されています。
労働者を特定する行為をした場合、派遣法違反として派遣先企業は行政指導の対象となります。
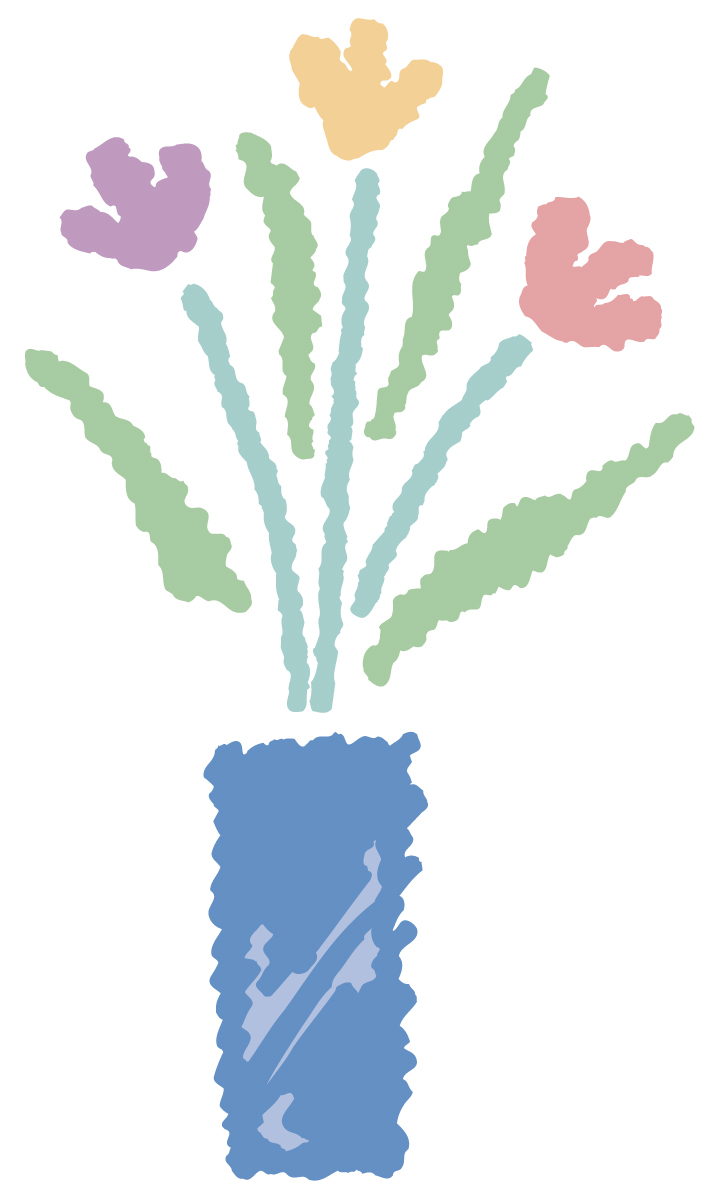
派遣の「顔合わせ」は「面接」ではないの?
派遣で働くとき、「顔合わせ」や「面談」というかたちで派遣先の責任者や担当者と面会する機会が設けられるケースがあります。
派遣先企業が派遣社員を選別する行為は禁じられていますから、この顔合わせはあくまでも、派遣社員が紹介された仕事を受けるかどうかの判断をするために行われるものです。
派遣会社の営業担当者から仕事を紹介されたとき、その仕事を受けるかどうかは職場の様子を見てから判断したい、受ける前に派遣先の担当者に色々と質問や確認をしたい、と思うことがあると思います。
そんな時、この顔合わせで実際の職場を見たり、疑問点を解消してから仕事を受けるかどうか決めることができます。

とはいっても実際に顔合わせの場で、派遣先の担当者から職務経歴や仕事上のスキルについて質問され、「面接をされているようだ」と感じた派遣社員の方も少なくありません。
また、顔合わせをした後、派遣先から就業を断られるというケースも少なからずあります。
そうならないためには「面接じゃないから落とされることはない」と気を抜くことなく、身だしなみを整える、挨拶をきちんとする、正しい敬語で受け答えをする等の基本的なマナーをしっかりと守りましょう。
聞かれたことにはハッキリと答え、不明点があれば遠慮せずに質問しましょう。
仕事のスキルに関して過大評価されてしまうと、与えられる仕事があなたの実力と合わず、あなた自身も辛い思いをしますし周囲にも迷惑をかけてしまいます。
その一方で謙遜しすぎてしまったために、スキルが足りないと判断されてお断りされてしまっては勿体ないですよね。
そのため、仕事のスキルに関する質問に答えるときは、あなたのスキルや仕事上の経験について正直にありのままをお話ししましょう。
顔合わせの場には、派遣会社の担当者が同席することがほとんどです。
不安なことがあれば事前に担当者に確認しておきましょう。
<
目次
当サイトはリンクフリーです。管理人の許可なく自由にリンクを張って頂いて問題ございません。
