派遣社員の受け入れ期間制限ルール
派遣の「3年ルール」という言葉を耳にしたことはありませんか。
派遣労働者は同じ事業所や同じ部署においては、3年を超えて働くことはできないというルールです。
定められた派遣期間を過ぎた翌日のことを抵触日といい、派遣社員は原則として抵触日を過ぎて働くことはできません。
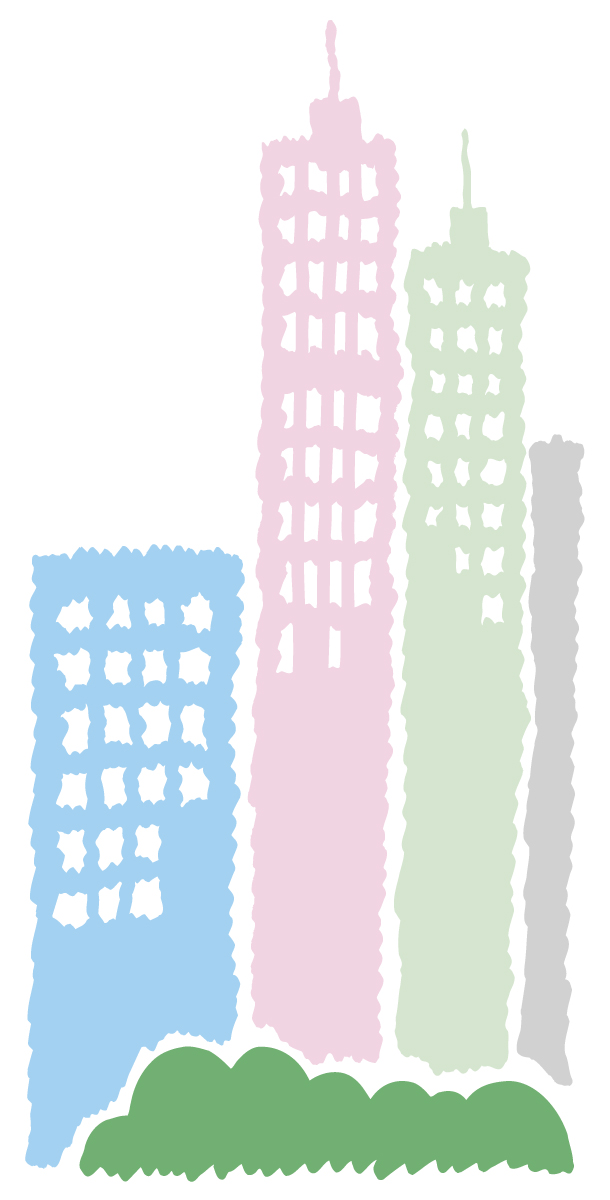
この3年という期間の制限には、「個人単位」と「事業所単位」の2つがあります。
個人単位の抵触日は、派遣社員が働くことのできる期間の制限をいいます。
事業所単位は、その事業所が派遣社員を受け入れることのできる期間の制限をいいます。
注意しなければならないのが、個人単位よりも事業所単位の期間制限の方が優先されるという点です。
例えば自分が派遣社員として派遣先企業で働き始める前に、他の人が派遣社員として同じ事業所で2年間働いていた場合、自分が働くことができる期間は残り1年となります。
この事業所単位の期間制限は、派遣先の事業所の過半数労働組合等から意見を聴いた上であれば、3年を限度として延長することができます。
リクナビ派遣(PR)

また、以下の場合は例外として3年ルールが適用されません。
- 派遣社員が派遣元に無期雇用されている場合
- 派遣社員が60歳以上である場合
- 終期が明確な有期プロジェクトに派遣される場合
- 日数が限定された業務の場合(1ヶ月の勤務日数が、派遣先の通常の労働者の半分以下かつ10日以下)
- 産休、育休、介護休業などを取得する人の代わりに派遣される場合
雇用の安定を図るための措置
上述した「3年ルール」のため、派遣社員は基本的に最長3年で派遣契約が切れてしまい、次の仕事を探さなければなりません。
その負担を軽減するために、「雇用安定措置」が設けられています。
同じ組織に継続して3年派遣される見込みとなった場合には、派遣会社は派遣社員に対して、以下の①~④のいずれかの措置を講じる義務があります。
(就業見込みが1年以上3年未満の場合は努力義務となります。)
① 派遣先への直接雇用の依頼(派遣先が同意すれば、派遣先の社員となります)
② 新たな派遣先の提供(その条件が派遣で働く方の能力、経験等に照らして合理的なものに限ります)
③ 派遣元での派遣労働者以外としての無期雇用
④ その他雇用の安定を図るための措置(紹介予定派遣の対象となること等)
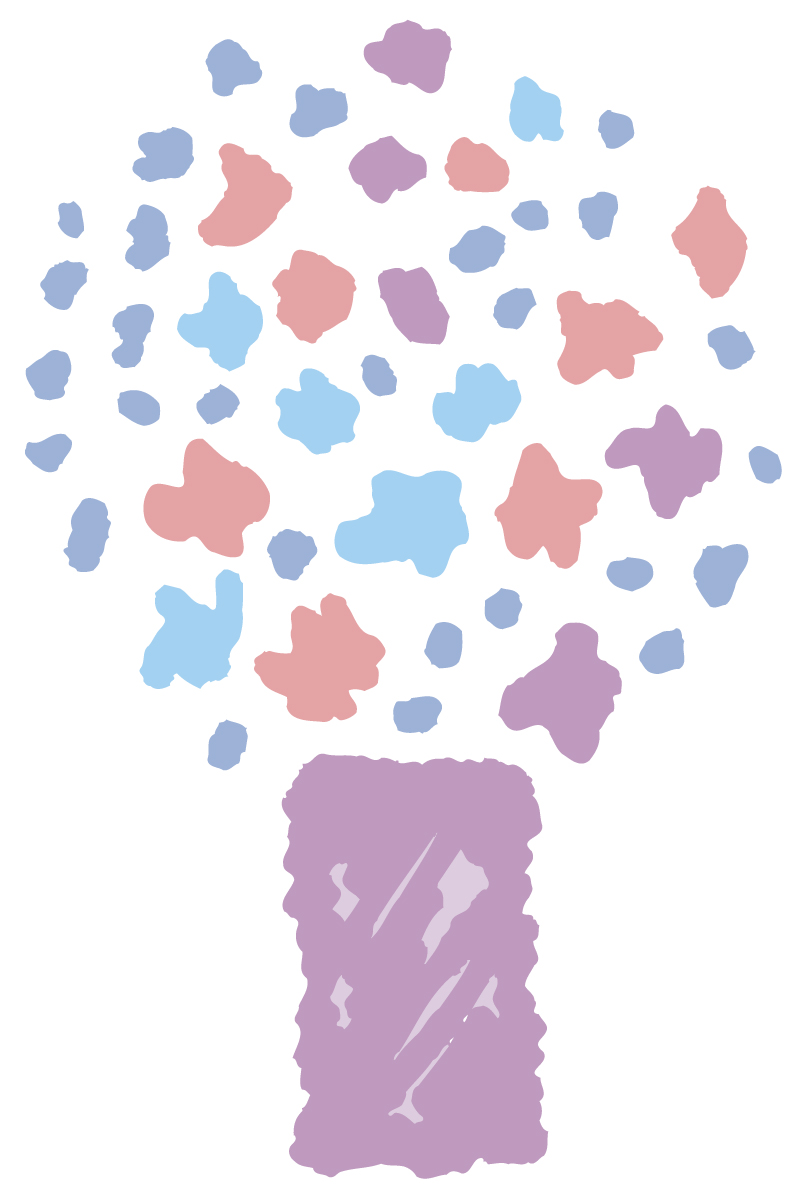
派遣会社は面談等を通じて、派遣社員に対し、派遣終了後も継続して働きたい気持ちがあるかどうかを確認します。
雇用安定措置を受けたいのであれば、面談にて継続就業を希望する旨を伝えましょう。
雇用安定措置①~④のうち、どの措置を講じてもらうかは派遣社員が選ぶことができます。
リクナビ派遣(PR)
労働契約申込みみなし制度とは
労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が違法派遣をした時点で、派遣先が派遣社員に対して、派遣元事業主との労働条件と同じ労働条件で直接雇用の労働契約を申し込んだものとみなす制度です。
(派遣先が違法派遣に該当することを知らず、かつ、知らなかったことに過失がなかったときを除きます。)
派遣社員がこの労働契約を承諾した場合、以後は派遣先と派遣社員との直接雇用となり、給与の支払いは派遣先が行います。
派遣先が労働契約の申込みをしたものとみなされた日から1年以内に派遣社員がこの労働契約を承諾する旨の意思表示をしなければ、労働契約は成立しないという点に注意が必要です。

「労働契約申込みみなし制度」の対象となる違法な労働者派遣
① 労働者派遣の禁止業務(港湾運送業務、建設業務、警備業務、医療関連業務、士業)に従事させた場合
② 無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合
③ 期間制限に違反して労働者派遣を受け入れた場合
④ 労働者派遣法等の規定の適用を免れる目的で行われるいわゆる偽装請負の場合

リクナビ派遣(PR)
目次
当サイトはリンクフリーです。管理人の許可なく自由にリンクを張って頂いて問題ございません。
